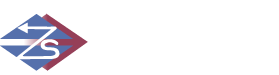やきものの世界
2019.06.30
こんにちは!社会科の伊藤です。
梅雨らしい日が続いています。
非常に湿度が高く、昼はじめじめして蒸し暑いですね。
そんな今週末、お出かけ日和とはいきませんでしたが、屋内であれば関係ないですよね。
愛知県は自動車工業の街であると同時に、窯業の街としても有名です。
「窯業」とは陶磁器などを製造する工業です。
陶磁器のことを「せともの」と言うことがあります。
その由来にもなっているのが、文字通りの愛知県瀬戸市です。
瀬戸市には、愛知県陶磁美術館があります。
現在、インダス文明の遺跡から出土した土器の企画展が開かれているということで、初めて瀬戸市を訪れました。

撮影可の展示もいくつか存在したので、記念に写真に収めてきました。
紀元前4500年~3500年頃の非常に古い時代の土器をはじめ、インダス文明前期~インダス後までに至る多数の土器が展示されており、中々に興味深い企画展でした。
土器には当時家畜として飼われていた瘤牛(こぶうし)や山羊といった動物、インダス川に住んでいたであろう魚や、菩提樹といった植物などがデフォルメを施し文様化されて描かれていました。
多くの土器は当然ながら、食物の煮炊きや貯蔵に使用されるものです。
その目的のためだけであれば、絵を描いたり、模様を描いたりする必要はありません。

にもかかわらず、わざわざ絵を描いたり、細工を施したりして、土器をただの「道具」ではなく、美しい「作品」に仕上げています。
この他にも陶磁美術館には、常設展として世界各地の土器や陶磁器が展示してあります。

日本、中国、朝鮮半島、東南アジアや中南米、ヨーロッパなど世界各地で作られた様々な焼き物を実際に見ることができました。

日本の縄文土器や土偶、弥生土器、渡来人によってもたらされた須恵器や弥生土器の流れを汲む日本の土師器など、
中学校の歴史の教科書や資料集にも登場する有名な土器の数々も、間近で見るのと写真で見るのとではそこから伝わってくるものが全然違うようです。

人間は芸術の心を持ち、実際にそれを表現できる唯一の動物なのだと思うと、改めて人間が本来的に持ち合わせている
美しさや偉大さを感じることができます。
「源泉を汲む」ことの大切さがまた少しわかったような気がしました。