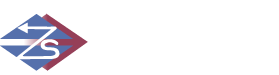新しい?発問
2025.10.10
塾でも学校でも、授業中に各先生が様々な発問をすると思います。
私の授業では、
体感ですが、他の先生より発問が多いのではないか、と思っています…。
普段の授業では、
『○○は好き?嫌い?』
『□□は知ってる?』
『△△はどんな意味だと思う?』
といったように、
状況に応じて、生徒の知識の確認や興味のあるものを取り入れて進めるようにしています。
そして、
今回、普段はしない発問をしてみました。
それは、
『この範囲から、どんな問題をつくれる?』
といったものです。
今の中学生、なかなか『頭を使った勉強』ができていないことがあります。
教えられたこと、課題で勉強したことはできるのですが、内容や問い方を変えると、わからなくなってしまう生徒がいます。
また、
学校のテスト勉強でも、
どこがテストに狙われるのか、
どんな出方がされるのか、
予想して勉強するのと、
闇雲に課題をこなすのとでは、
全く違います。
今回、知立校と碧南校の生徒に聞いてみると、
『○○の穴埋め!』
『□□の意味!』
『△△を答えさせるもの!』
といった答えが返ってきました。
たしかに、出題されると思います。
しかし、答えてもらったものは、配点が比較的低いものです。
より高得点に結びつく問題は、
『○○と□□の違い』に着目した問題です。
なぜ違いができるのか、
違いがあることによる影響は何か、
といったところに注目できると、勉強の質も変わってきます。
模試や入試でも、
『○○は何ですか?』
といった一問一答形式の問題は、ほとんどありません。
社会であれば、
歴史の年表や背景、日本と世界の比較
地理のグラフの読み取り、各国や地域の特徴
公民の用語やしくみの理解
といったように、
知識があることを前提として、
『いかに知識を使えるか』という問題が出されます。
次の11月のテストは、中学3年生にとって、中学校生活最後の定期テストになります。
悔いの残らないように、勉強の質を高めて、早め早めの準備をしていきましょう!
1、2年生も同様に、今のテスト勉強が、これからの自分の勉強方法になっていきます。
なかなか上手くいかないときは、どこか改善できないか考えて、取り組むことで、より成長できるのではないでしょうか。
近藤